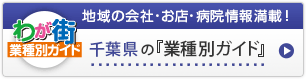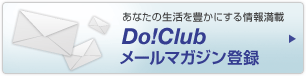八街市特集
[千葉県]
千葉県北部のほぼ中央に位置し、東京から50キロメートル圏内、京葉工業地帯からは20キロメートル、成田国際空港から10キロメートルの位置にあります。東は山武市に接し、西は佐倉市に、南は東金市・千葉市に、北は酒々井町・富里市にそれぞれ接しています。
市の広さは、東西に短く約7.7キロメートル、南北に長く約16キロメートルあり、面積は74.94平方キロメートルです。
市の中央部は市街地を形成し、周囲には平坦な畑作地帯が広がっているほか、南西部および北部に水田地帯が点在しています。
八街市のいいトコ!!
八街市で憩い・楽しむ
お釈迦様が寝ている山
法宣寺付近の山を望む景観は、まるでお釈迦様が寝ているように見えることから、地元では「寝釈迦」と呼ばれています。

迫力満点の釈迦涅槃図
根古谷地区にある法宣寺は、室町時代に創建された八街第二の古寺。毎年3月15日、16日の2日間のみ、寺が所蔵する「釈迦涅槃図」が一般公開されます。
この涅槃図は、彰義隊の一員であった作者が、幕末の騒乱で戦死した人々の鎮魂を願って描いたものといわれています。その大きさは本堂の天井から吊さなければ広げることができないほどの大きさで迫力満点です。

八街市の名所・文化
千葉黎明学園生徒館
千葉黎明高等学校の前身である、八街農林学園が創設された翌年の大正13年に講堂兼武道場として建設。この館においては、高橋是清閣下(第20代内閣総理大臣)が2度講演を行いました。平成25年に国登録有形文化財(建造物)に登録されました。(提供 千葉黎明学園)

文違麦つき踊
明治の始めごろ、開墾で入植した人々が麦を精白する苦しい作業のなかから生まれた唄と踊り。明治20年ごろから文違地区でお盆などに踊られてきました。

榎戸獅子舞
寛永年間(1624~1643)、佐倉城主の土井利勝が、村民に娯楽を与えるために佐倉地方から導入したと伝えられています。

塩古ざると製作資料
江戸時代ごろから農家の副業として生産・販売されていた篠竹製のざるです。すでにその技術は途絶えてしまいましたが、郷土資料館に良好な状態で保存されています。

根古谷の湧水
市内に残された数少ない湧水。根古谷城址の近くにあります。

御成街道跡
慶長18(1613)年、徳川家康が東金へ鷹狩に行くために造成させた船橋―東金間を結ぶ街道です。八街の沖地区では造成当時の姿をとどめています。

カタクリ群生地
カタクリは、ユリ科の多年草で、比較的冷涼な雑木林の北斜面の林床部に自生しています。以前は川上地区のいたるところに自生していましたが、開発や里山の放置などの理由により大部分が消滅した中で、砂日枝神社の境内地のカタクリは貴重な群生地となっています。